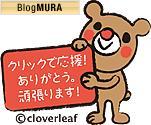|
20080511~
13と7と11の倍数の論理積は13と7と11の積の倍数である。
和ァ・・・
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
小さな電車を走らせたりできないかなあ(誘導電動機)
audacityが無理ならscilabにやらせるぅ・・・ですかねえ? Excelのマクロでjpgの読み書きができるのに 同じくexeファイルが出ないscilabに音声ファイルの読み書きができないわけがないんですよ よく考えたら信号処理・制御工学用の言語なんですし イヤホンジャックでたーのしーことさせたいなあ まあ増幅云々は後段にま か せ て 動的逆立ちしながらモータで歌うロボットとかできないかなあ あ、そういえば、誘導電動機って、それ自体をセンサーとして使うことってできるんだろうか やっぱ自走する楽器ってロマンだよなぁ けいおんとかばくおんとか、響けユーフォニアムとかはがねオーケストラとか見てるとつくづくそう思う
顔がでかくて(ガウス)、首が太くて(アンペール)、足が短くて(ファラデー)…
ちょっとずんぐりまっくす(笑)な感じする頑丈な媒質してるのがフォトンです 木の…木ぃにも登らなアカンし(μ=μ0)、 水にも入らなアカンし(μ≠μ0)、 どこでも…こう振動したりできるような媒質になってるので… 磁石の模様は…丸っこい輪っかが磁力線に沿って散らばってますやんか(大前提※)、 その丸っこい輪っかの中に、さらに点々があるのがコイルの模様です ふぇるでぃなんと・ぶらうんどうぶつえん クォークニオンおにいさん(せるん)
アイソレータとダイオードは意味は似てるけど構造と用途は全然違う
フォトカプラとアイソレータも意味は似てるけど用途は全然違う 一方で、ダイオードとフォトカプラは意味は似てないけど構造が近い なんかもう逆に違うわ。ちゃんちゃらおかしいわ。 エディントンのイプシロンちゃんっていう名前のサーキュレータの各端子にアイソレータとフォトカプラとダイオードをそれぞれ突っ込んだぐらいちゃんちゃらおかしい 小樽小樽すきすき ・ライムこしょうで食べてね なんなんだよ ・ブラッドイチィー なんなんだよ ・じゃあ日向縁は? 光合成? あー惜しい。なんなんだよ三連発させたかったのに セイバーマリオブラザーズ、唯も結衣も好きそうだよなー scilabのビジュアルシミュレータうごかねええええwwwwww
そうさバーチャルショート<偉大なる航路>も悪くはないかな
ステイしがちな電子だらけの頼りない流れでも きっと飛べるさOP-AMP のタイムパラドックスによるノイズの増幅=この宇宙のすべて そんなわけで昨年末の続きです。 440Hzの正弦波を作ります。 次に、最大増幅率で増幅します。(クリッピングを有効に) 一旦音声ファイルとして書き出し、編集中の窓を閉じ、書き出したファイルを読み込みます。 カットオフ周波数を450Hzに、48dB/オクターブの勾配でローパスフィルタにかけます。 ほぼ正弦波に元通り。 あの世とこの世で 「デジタルワールド(離散)」かつ「リングワールド(周期)」なんなー
知り合いの整骨院に、ヘルストロンがあるのです。
9kVを印加して1mAを流しているらしく 人が最大4人くらいまで利用できるらしいんですが これが不思議なことに何人乗ろうがメーターがピクリとも動かないんです。 大地とは碍子でなかば絶縁されていて 碍子にあまり詳しくない僕は、どうして碍子があんな腸の柔毛のようなヒダヒダの形をしているのか気になりまして ぐぐったらスパーク防止のためらしいことがわかりました。 そのうえ、交流の場合は表皮効果を考えてあのような形にして碍子の表面積を増やすことで 電流の経路を少しでも長くしているらしいんですが、 だったらどうして直流用の碍子にもヒダヒダがあるのかよくわかりません あ、雨風で汚れないようにってのもあるんすか。そっか。なら納得だ おそらくヘルストロンに印加されている電圧は交流だとは思うのですが いったい何ヘルツくらいなのかが気になりまして モデルを考えてみました。 人が乗っても乗らなくても電圧V・電流Iの値がほぼ変わらないということは 電極間にはほぼ一定値の抵抗とコンデンサが並列に並んでいると見てよさそうな気がします。 電極の面積S約600㎠と、電極同士の距離d約2メートルを考慮し 誘電率ε0と抵抗率ρに「空気」を当てはめてみると 確か、 角周波数ωだったら20krad/sを超えてるんですが 2πで割った周波数fだとギリギリ可聴域であるらしいです。 f=(√((ρdI/S/V)^2-1))/(2πρε0) ダメになってもいいクリスタルイヤホンをつなげて音を聞いてみたいです。 一方、ヘルストロンとセットで「検電器」というものがあって 検電器そのものに機能はほぼなく おそらくただの抵抗をかました静電気除去棒のようなものだと思うんですが 検電器を患部に当てることで、検電器を通じて弱化された電流が検電する人間の体を伝って流れて、それで患部をよりピンポイントに治療するという考え方のようです。 だからぶっちゃけ、 僕が静電気除去棒を持ってヘルストロンに乗り、外部の接地された物体と障るだけで、指先を治療している、 と、そういうことだと思います。 しかし、検電しているかどうかを明確にしたいため、表示と音を発生させる簡単な回路がついているようです。 まあこれも、ぶっちゃけていうと、ちょっと高い静電気除去棒と同じで、ちゃんと除去しているかどうかモニタする機能がついているからちょっとだけ高いよ といっているようなものだと思います 問題は、その高周波をどのように可視化・可聴化しているかなのですが 20kHzより少し下の正弦波を音源と仮定した場合、 かなり高い音で、きれいなフルートの音色(時報ともいう)に近いものが出るはずなんです。 実際にはそのような音ではありません。 また、割と昔から置いてあって、大きくて重いものなのでそんなにたやすく交換できる代物でもないようです。 LEDもまだ用いられておらず、昔ながらの電球のように見えます。 それでもなお、音と同期して光っているように見えます。 20kHz程度だったら点滅は見えず、点灯しているとしか見えないはずだと思うのですが。 (自転車のLEDでさえ、点「滅」するのは「ゆっくり」漕ぎ出した時だけです) そこで思ったのが、デジタル周波数逓倍器か、電磁ブザーです。 アナログの周波数逓倍器は集積度の高いものになってしまうでしょうし、回路も複雑で、メンテナンスがしづらい気がします その点、デジタルの周波数逓倍器だったら、LSIよりも集積度の低いIC程度で賄えそうな気がします しかし、どちらかというと僕は電磁ブザーのような気がするんです。 デジタル化して矩形波になったとしても、あのようなジ・ジ・ジといったノイズのような音は出ないと思うのです。 それに、信号を電源として用いた電磁ブザーだったら、ブザーの機械的仕様に合わせて好きな周波数成分にできますし そこから電球にも分配してやれば、比較的簡素な回路構造で済むと思うのです。 さて、まだ1つ問題がありまして、 その電磁ブザーは直流で動くのか、それとも交流でも動くのかという点です。 もし直流でしか動かないのであれば、整流平滑回路が必要になります。 が、交流電源でもよいのであれば、より回路を簡素化できます。ブザーと電球だけででほぼ完成します。 たとえば交流をアナログの直流電流計で測るとゼロが表示されます。(カドーてっぺんとか) しかし、交流電流計だとちゃんと実効値が表示されます。 つまり、電圧や電流自体が平均ゼロでも、伝達される電力は平均ゼロにはならないことを利用した電磁ブザーがあるのかどうか、それが知りたいのです あのヘルストロンはかれこれもう25年はあそこに鎮座していると思います。 技術の進歩で、アレを交換したら色々な部分の設計が変わることでしょう。 新しい技術を取り入れると思いますし、むしろ古い部品はもう生産していないと思います もし万が一アレが故障して部品交換となったら、買い替えるほかないかもしれません そうなると高くつくんじゃないかな 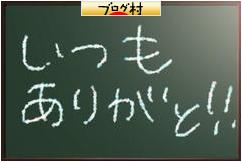 にほんブログ村
とりあえずほぼ理想状態で考えてみて、オペアンプとコンパレータは同じものであるとしよう
増幅率Aoは無限大と指定せずに、またそれはイマジナリーショートでもないことを意味する。 とはいうものの、増幅率AoはViの関数なんだけども、そこはちょっとだけ理想的に、デルタ関数であるということにしておこうか。 つまりAo(Vi)=δ(Vi)というわけで。 これなら飽和状態も表現できるかもしれない。 そうした上で、外部からフィードバック抵抗Rfと、オペアンププラス側前段の抵抗Rxをつけてやると、 このデルタ関数にヒステリシス幅が生じるモデルを考えられるかもしれない。 反転増幅回路に似てるんだけども、極性だけ反転していて、かといって非反転増幅回路というわけでもないフィードバック回路のアレ これで、入力電圧のヒステリシス幅ΔVh=(Voh-Vol)*Rx/(Rx+Rf)と ヒステリシス中心の電圧Vh=(Voh+Vol)*Rx/2/(Rx+Rf)を再現できるだろうか どうもデータ不足で仕方ないんだけど、 このヒステリシス中心とかいうやつは入力ではなく出力の電圧の中心電圧だろうか 示強が縦で示量が横軸だとすると Vinを縦にして、抵抗にVoutをかました負荷電流ILを横にしたら、p-V図みたいになるだろうか いや、今一つだな。時間がない 電流Iではなく電荷Qのほうがいいかもしれない いよいよ他分野の記号が混ざってきた。  にほんブログ村
メムキャパシタとメムインダクタってなんだよ!!!なんかしらんけど開発中らしくて、もうすぐ出来上がるとかなんとか。
でも図解ないよ!? 読者の創造しさを高めることに定評のある日経サイエンスにしても図解少なすぎだろぉ!? っていうか、メモリスタがミッシングリンクだったって話はどうなったんだよ!?そんな時代もありましたってか!?おいー! 定義だけぽいーって渡されて中身がわからないのが一番いやなんだよぼくは!!! ====== ところで、ハルロックという漫画をひとまず第1巻だけ買ってみました。 確か、漫画からではなく電子工作か科学的な何らかの雑誌からこの漫画を知ったような気がします 気づいた頃には連載最終回で、 買ってみることにしたんですね こんな眉毛ほったらかしのヒロイン見たことねえ! おしゃれに費やす時間をまず無駄と仮定してから漫画が始まるとかすげえ・・・! 俺達はこんな漫画を求めていたのかもしれない。 はるちゃんの日常生活を垣間見ると、表紙に写ってるはるちゃんの眉毛の違和感なんかどっか飛んでった!めっちゃ親近感! まあ、そういうわけで、電子工作する人間を擬人化・女体化した ℃りけいに似たタイプの擬人化漫画だと思われますが 電子工作に入門したい人からすれば入門の本っちゃ本なんですが 電子工作を一旦諦めた人目線の漫画でもあるような気がするんですね うっかりしてたら技術がこんなに積層されてしまっていた!どうしようたすけてウラたろ~す! みたいな。 ヒロインであるはるちゃんに電子工作の芽を与えた先生の言葉が気になります。 俺はコンデンサにはあまり興味が無い んだとコノヤロウひとっ走り屋上までコサックスクワットつきあえや あ、間違えたそこじゃない セラロックに萌えた時代もありました!´皿` 今は違うのかー!? どうにも意味深なこの一言。 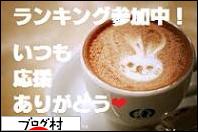 にほんブログ村
前回のあらすじ
カンタ「やーい!おまえんちの家計簿、/オッペアーンプ\!」 サツキ「メイ、このままじゃまずいわ。全財産表示の出力がジゴボルトを超えそうよ!」 メイ「かみなりさま~!」 サツキ「なにかいい案はないものかしら・・・?」 メイ「ちょっとトロロんとこいってくる~」 サツキ「ちょっとメイ!私もいく!」 メイ「ねえトロロ、じごぼるとって、なに?」 トトロ「ぶぉぉぉぉぉぉぉ!」 小トトロ「ピュ」 メイ「これ、くれるの~?」 サツキ「メイってば、ちょっと待って・・・ あ。これは・・・どんぐりと、松ぼっくり?それに、みかんにメロンに夕張メロンにぶどう・・・タロスにレモン、バナナにドリアンまで!」ナシとリンゴ、おめーの汁ただの金メッキです メイ「どんぐりをいつつわたせば、まつぼっくりをひとつくれるゥ??」 サツキ「どんぐりの戦闘力はモブぼっくりの5分の1なのね。はっ!これはわらしべプロトコル!?そうだ、それよ!」 サツキ「メイ、私にいい考えがあるわ!ついてきて!」 メイ「メイまだここであそぶ~」 サツキ「じゃあ夕ごはんまでには帰るのよ!」 お父さん「なるほど、直交関数系である三角関数を使って、金額を硬貨別に振り分けたわけか~。」 サツキ「メイの名案なの!どんぐりの5倍の戦闘力を持った松ぼっくりがいてね(chry ここにファンクション・ジェネレータがあります。周波数を、32Hzを1円玉、64Hzを5円玉、128Hzを10円玉、256Hzを50円玉、512Hzを100円玉、1024Hzを500円玉、2048Hzを1000円札、4096Hzを5000円札、8192Hzを1万円札、16.384kHzを5万円札、32.768kHzを10万円札、65.536kHzを50万円札に見立ててみたの!これで周期関数を作れば、たった1つの関数でいつでも復調が可能になるわ!しかも、出力の電圧が上がりすぎて感電や放電する心配もなくなる!」2000円札、おめーのせきねぇです お父さん「従来1ジゴボルト必要だったのが新しいシステムだと高々2キロボルトで済むわけか これで我が家の家計簿も安泰だね!早く母さんに知らせなきゃ!!システムを構築するのは母さんの仕事だからね!」 ト、トロ・ト、トーロ♪  にほんブログ村 父さん「どうかな?これがホントの量子化。なんつって」 母さん「メンドイ、意味が無い、殺す気か。却下q^^」
ログ・ホライズンを見てると、生産性のある人間ってなんだろう?って思えてくるんですよね。
こんな感じの、外部にほとんど影響しないネトゲ廃人や、ニコニコ技術部の「変態に技術を与えた結果がこれだよ」な人たちも 決して非生産的ではなく 他人へのモチベーションを与えているという意味ではいわゆる正規の仕事をしている人と同等かそれ以上の働きをしていると言えなくもないじゃないですか。 それでいて責任感を極めて薄い状態に維持でき、ストレスが少ない環境でのびのびしてられるので なんというか財力・能力的に選ばれし存在と勘違いしそうな感じの人だけが行えるわけで 「働いたら負けかなと思ってる」の意味がやっとわかったような気もします ちょっと違う意味で、ロボットにすべてを任せて何もすることがない世界ともいえますしね ======= 羽根車つきクルックス管、いじってみたかったなぁー あれでしょ?コンボ技できるんでしょ? 磁界vs電界の形で、陰極線を羽根車の上に当てるか下に当てるか競うドリームマッチができるんでしょ!? その辺のニッチな需要に答えられる環境っていいよなぁー 低周波リサージュ図形写したオシロスコープの中で羽根車がうじゃうじゃ回ってたらシュールでいいなぁ 磁界vs電界の信号源はモータージェネレータから出てくる全波整流あるいは、イヤホンジャックから出てくるPWM制御信号とかで ついでにブザーとスピーカーにも出力してやって、「ほらどっちからも音が聞こえるでしょー?ACでもDCでもあるんだよ」的な。  にほんブログ村 こんな感じでバレーボールの得点板に、サーブ権とローテーションも表示してみたんです。 でも、Excelで一括処理するにはスペースというか無駄スペースが多すぎるので、 右半分を省略したのがこれ、タイプ・「ウチの家計簿」です。 「加算」の部分はテキトーに一様乱数使いました。 -1~1の範囲なので、2*rand()-1です。勝手にガタガタ再計算言わないように、値だけ切り貼りしました。 整数のほうの加点は 加点(整数)=sign(加点) です。1か-1、つまり味方チームか敵チームに点が入ることを意味します。 乱数できっちりゼロが出る可能性は省略しました。 得点の式はこうです。 得点=1つ前の得点+加点 つまり積分のようなものですね サーブ権は得点の微分なので、加点と同じということになります。 ローテーションはサーブ権を更に微分したようなものなので、 rot=今のサーブ権-1つ前のサーブ権 となります。 この表のマイナス部分を右敵方チームに分配してやると、先ほどのこの表に戻ります。 グラフにするとこうなります。 これをブレッドボードに実装する前に、流れ図を書いておきましょう。 左味方チームと右敵方チームの2本のラインがあります。 味方と敵のスイッチは反転した上で連動しており 味方が勝つと味方ラインに電圧がかかり 敵が勝つと敵ラインに電圧がかかります。 スイッチはトグルスイッチの予定です。 この信号は「加点」という扱いになるため 積分器を用いて一旦積分されて、「得点」になります。 それから改めて微分されることで、サーブ権になります。 正確には微分して更に2値量で出力したいので、コンパレータをはさみます。 割りとどうでもいいことですが、コンパレータの出力のレベルをシフトするためにバイパスコンデンサを使用するつもりです。 それを更に微分器で微分することで、ローテーションの電圧値が得られます。 積分器、微分器、コンパレータはそれぞれ、次のようになります。 実装経験がほとんどないため、コンパレータとオペアンプの違いがよくわかってません/^o^/ズコー 特にパルス波で同期とらなくてもちゃんと出力してくれるんじゃねーかなーと期待。 のはずです・・・誰か暇だったら作って^^  にほんブログ村 |
カレンダー
カテゴリー
最新CM
[08/08 さつ香]
[12/30 buy steroids credit card]
[09/26 Rositawok]
[03/24 hydraTep]
[03/18 Thomaniveigo]
最新記事
(01/01)
(03/19)
(03/18)
(03/18)
(02/23)
(02/14)
(02/12)
(01/03)
(09/23)
(09/23)
(02/11)
(05/30)
(05/28)
(05/28)
(05/27)
最新TB
プロフィール
HN:
量子きのこ
年齢:
44
HP:
性別:
男性
誕生日:
1981/04/04
職業:
WinDOS.N臣T
趣味:
妄想・計算・測定・アニメ
自己紹介:
日記タイトルの頭についてるアルファベットは日記の番号です
26進数を右から読みます 例:H→7番目、XP→15(P)×26+23(X)=413番目。 A=0とする仕様につき一番右の桁はAにできませんのでご了承くださいズコー
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(05/11)
(05/11)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/14)
(05/14)
(05/14)
(05/14)
(05/16)
(05/16)
(05/16)
アクセス解析
|